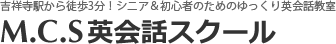シニア層に誤解の多い"location"《シニア英会話教養講座》
英会話のレッスンをしていると「和製英語」による誤解を実感することがよくありますが、その中でも特にシニア層に顕著なのが"location"という言葉です。"location"は〔名詞〕で「位置・位置づけ・立地・場所」とい […]
「いい人」は"a good man"? "a nice man"?《シニア英会話教養講座》
私ども「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアクラスでたびたび話題に上る"good"と"nice"の違いについてお話しします。 両者はほとんど同じ意味と考えても差し支えはないのですが、微妙にニュアンスが違います。 例え […]
Can you speak English?の話《シニア英会話教養講座》
私ども「吉祥寺MCS英会話スクール」のとあるシニアクラスで、先日「"can"の使い方」についてレッスンをしました。 "can"は「~することができる」という意味の〔助動詞〕ですね。三人称単数の"s"などを気にしなくても […]
「インバウンド」の話《シニア英会話教養講座》
今日は8月15日。日本ではお盆休みのまっただ中。主だった観光地には外国からの旅行者も多く見られます。 私もこの夏は出雲大社に行ってきましたが、東南アジアやアメリカ(?)系の参拝者を大勢見かけました。 ここでは、コロナ […]
「ぬるいお風呂」《シニア英会話教養講座》
「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアレッスンで、先日話題になった事から引用させて頂きます。それは「ぬるめのお風呂に入る」という言い方です。 「ぬるい」といえば、"warm(あたたかい)"とか"not hot(熱くな […]
「ゆっくり・ゆっくりする」《シニア英会話教養講座》
「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアクラスでは、一週間の小さな出来事を簡単な英語で発表してもらうようにしています。 皆さんの話の中でよく出てくるのが、「家でゆっくりしました」("I stayed at home s […]
「可及的すみやかに」《シニア英会話教養講座》
近頃ニュースでよく聞くようになった言葉に「可及的すみやかに」というのがあります。具体的には、北朝鮮の人工衛星打ち上げに関連しての報道からなのですが、大変興味深い言葉だと思います。 「可及的」というのは「できるだけ・可 […]
「フィーチャーする」《シニア英会話教養講座》
最近時々耳にする言葉で「フィーチャーする」というのがあります。先日私ども「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアの生徒様から質問を受けたばかりですので、あらためてここで説明させて頂きたいと思います。 よく使われている「 […]
「サブスク」って何?《シニア英会話教養講座》
最近になって急によく耳にするようになった「サブスク」という言葉。 「サブスクってどういう意味ですか?」という質問が、私ども「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアの生徒様から寄せられましたので、この場を借りて簡単に説明 […]
「どうぞよろしく」はなぜ英語にないのか?《シニア英会話教養講座》
私ども「吉祥寺MCS英会話スクール」のシニアの生徒様からよく聞かれる質問として、「どうぞよろしくは英語で何というのですか?」があります。 以前にも書いたかもしれませんが、今日はもう一度その話を取り上げさせていただきま […]